「火垂るの墓(ほたるのはか)」は実話なのか?
多くの人がこの疑問を抱きます。
涙なしでは見られないと語り継がれるこの作品には、強いリアリティと胸に刺さる描写が詰まっており、視聴後に「これは本当にあった話なのでは?」と感じる人も多いのではないでしょうか。
火垂るの墓とは?作品概要とあらすじ
まずは簡単に作品の概要を振り返りましょう。
『火垂るの墓』は、1988年にスタジオジブリによってアニメ映画化された作品で、原作は野坂昭如(のさか あきゆき)による同名の短編小説(1967年発表)です。
舞台は太平洋戦争末期の神戸。
主人公の14歳の少年・清太(せいた)と4歳の妹・節子(せつこ)が、空襲によって家や母を失い、親戚の家や防空壕などを転々としながら過酷な戦争の日々を生き抜こうとする物語です。
しかし食糧不足や人々の冷たさ、体力と気力の限界によって、2人は次第に衰弱していき、やがて妹・節子が命を落としてしまいます。
清太もまた、戦争孤児として孤独の中で亡くなってしまうという、非常に悲しく衝撃的なラストを迎えます。
ジブリ作品の中でもファンタジー要素がほぼ皆無である現実そのものを描き、それでもなぜか見たくなるジブリファンの方が多いのではないでしょうか。
私もその一人で、夏の時期になると金曜ロードショーで放映される日を、毎年ついチェックしてしまいます。
見るのに勇気が要る作品でもありますが、見れば見るほど引き込まれ、見る時期によっても受け取るメッセージが変わる作品と感じます。
火垂るの墓は実話なのか?原作者野坂昭如の実体験が元に
結論から言うと、『火垂るの墓』はフィクションでありながら、作者・野坂昭如の実体験が色濃く反映された“事実に基づく物語”です。
作者の体験とモデルとなった妹
野坂昭如は、実際に戦時中に神戸で暮らしており、空襲によって家族を失いました。
彼には養子として共に暮らしていた妹がいて、その妹もまた栄養失調で亡くなったという壮絶な体験をしています。
野坂はその過去を長らく語らずにいましたが、ある日自分の過去を見つめ直すためにこの小説を執筆。
「戦争によって罪のない命が失われる現実」を描くことで、彼なりの贖罪と記録として『火垂るの墓』を世に送り出しました。
つまり、物語そのものは創作でありながら、根幹には実際にあった“妹を死なせてしまった少年の記憶”があるのです。
作品の内容が戦争という現実を描いているだけでなく、その根幹に作者のエピソードが存在することで、より作品のリアリティが感じられますね。。
火垂るの墓 清太=原作者 野坂昭如ではない理由
一方で、野坂自身は自著の中で何度も「これは創作だ」と明言しています。
というのも、現実の野坂少年は盗みや物乞いをして自分だけは生き延びました。
そしてそのことを深く後悔し続けており、作品の中の清太は、彼が「もし自分が違う選択をしていれば、妹を助けられたのではないか」という“理想化された自己”なのです。
この作品は、「現実の自分ができなかったことを、小説という形でやり直した物語」とも言えるでしょう。
ただ最終的には清太も妹は助けられず、、これは私個人の感想にはなりますが、どこまでも戦争の悲惨さを描く上では必要な締めくくりのように感じました。
火垂るの墓 映画版のリアリティと反響
1988年に公開されたスタジオジブリ版アニメ映画『火垂るの墓』は、高畑勲監督が手がけ、戦争アニメの金字塔と呼ばれる作品になりました。
映像化によって描かれる神戸の風景、空襲の様子、節子の体調の変化などはあまりにもリアルで、「トラウマ映画」として語られることも少なくありません。
また、ジブリ映画の中でも異色の“悲劇的な物語”として、何度も放送されるたびにSNS上では話題になり、多くの視聴者が「何度見ても泣いてしまう」「戦争の悲惨さが胸に刺さる」と語っています。
それだけの衝撃がこの作品と当時の戦争に纏わるエピソードとして語り継がれている、そんな影響力をこの作品には感じざるを得ません。
なぜ今も火垂るの墓が語り継がれるのか
現代の日本は戦争の記憶が風化しつつあり、実際に体験した世代も少なくなっています。
そんな中で、『火垂るの墓』は戦争の悲惨さを“感情”で伝える数少ない作品として、教育現場などでも取り上げられています。
特に、子ども視点で描かれているため、「戦争は大人の問題」ではなく、「誰もが巻き込まれる」という現実を強く感じさせます。
また、現代の孤独や貧困とも通じるテーマがあり、見捨てられる子どもたち」「支援が届かない社会」という側面からも再評価されています。
他人事ではない、そんなメッセージをこの映画からは感じます。
まとめ:実話としての火垂るの墓が伝えるもの
『火垂るの墓』は、「実話ではないが実体験に基づく物語」です。
戦争のリアルを感情で伝え、今もなお多くの人の心を揺さぶり続けるこの作品は、フィクションであること以上に、“本当に起こり得た現実”を想像させます。
私たちはこの作品から、戦争の悲惨さだけでなく、「誰かを守ることの重み」「命の尊さ」「社会の冷たさと温かさ」など、多くのことを学び取ることができます。
そして何より、「同じことを二度と繰り返さない」という決意を新たにするために、『火垂るの墓』はこれからも語り継がれていくべき名作なのです。


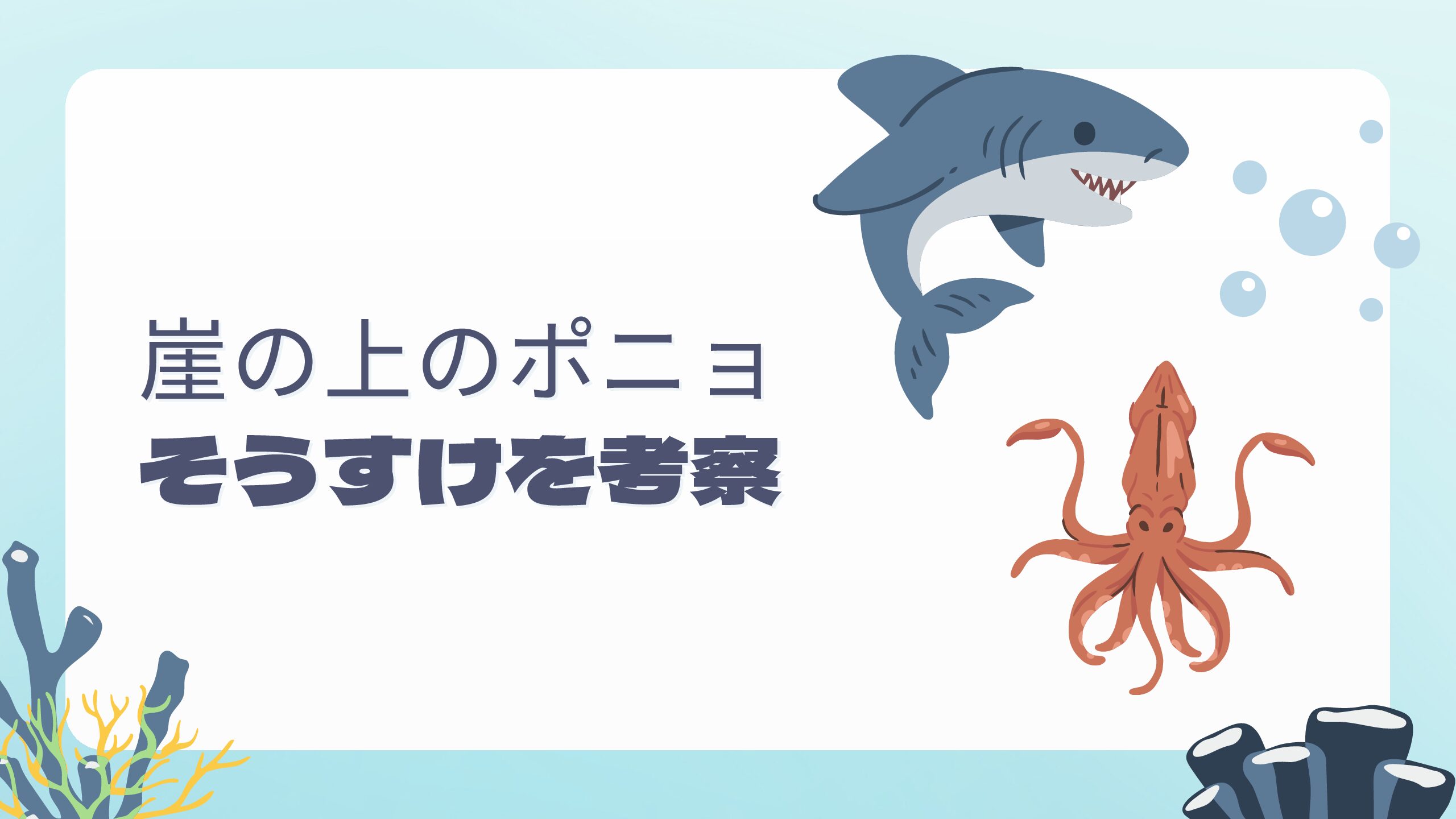
コメント